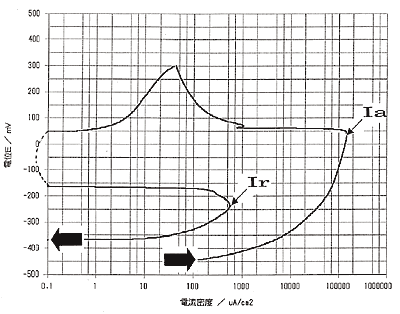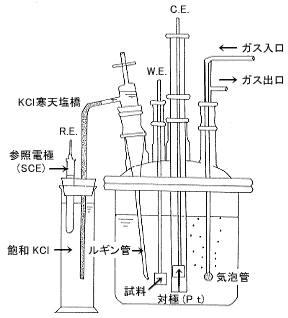1.電気化学的手法のご紹介
当社では、各種プラント,船舶,車両,橋梁,航空機等に使用される金属材料の耐食性評価を行なっています。その中でも、迅速に評価可能な電気化学的手法についてご紹介いたします。
電気化学的手法とは、イギリスの科学者ファラデーによって見出されたファラデーの法則を利用したもので、水溶液等における金属材料の耐食性を評価するものです。実際には、ビーカー内に対象となる金属試験片と水溶液を入れ、試験片に電圧を負荷します。実験には、複雑な腐食環境を単純化しますが、可能であれば実環境を再現して行います。
2.JISにおける測定法
JISにおいては以下のような電気化学測定法が制定されています。
- ステンレス鋼の孔食電位測定方法(JIS G 0577)
- ステンレス鋼のアノード分極曲線測定方法(JIS G 0579)
- ステンレス鋼の電気化学的再活性化率の測定方法(JIS G 0580)
他に、下記の情報を得ることも可能です。
- 自然電位
- 全面腐食環境における腐食速度の推定 等
3.電気化学的再活性化率の測定の例
オーステナイト系ステンレス鋼は、550~800℃程度の高温域で使用した場合、鋭敏化という組織変化を起こします。鋭敏化したステンレス鋼は粒界腐食感受性が高く、本来より耐食性が劣化した状態となります。 通常、鋭敏化のおおまかな程度を調べる方法として、しゅう酸電解エッチング試験(JIS G 0571)が適用されますが、さらに定量的なデータを得る場合に、電気化学的再活性化率測定を行います。
下図は、JISの電気化学的再活性化率測定法に基づいて得られた往復アノード分極曲線図です。こうして得られた最大アノード電流密度(Ia,Ir)の比から再活性化率(Ir/Ia)を求めます。 再活性化率は鋭敏化の定量値として表示されるため、例えば使用部材の部位別の鋭敏化進行状況を確認することなどに使われています。